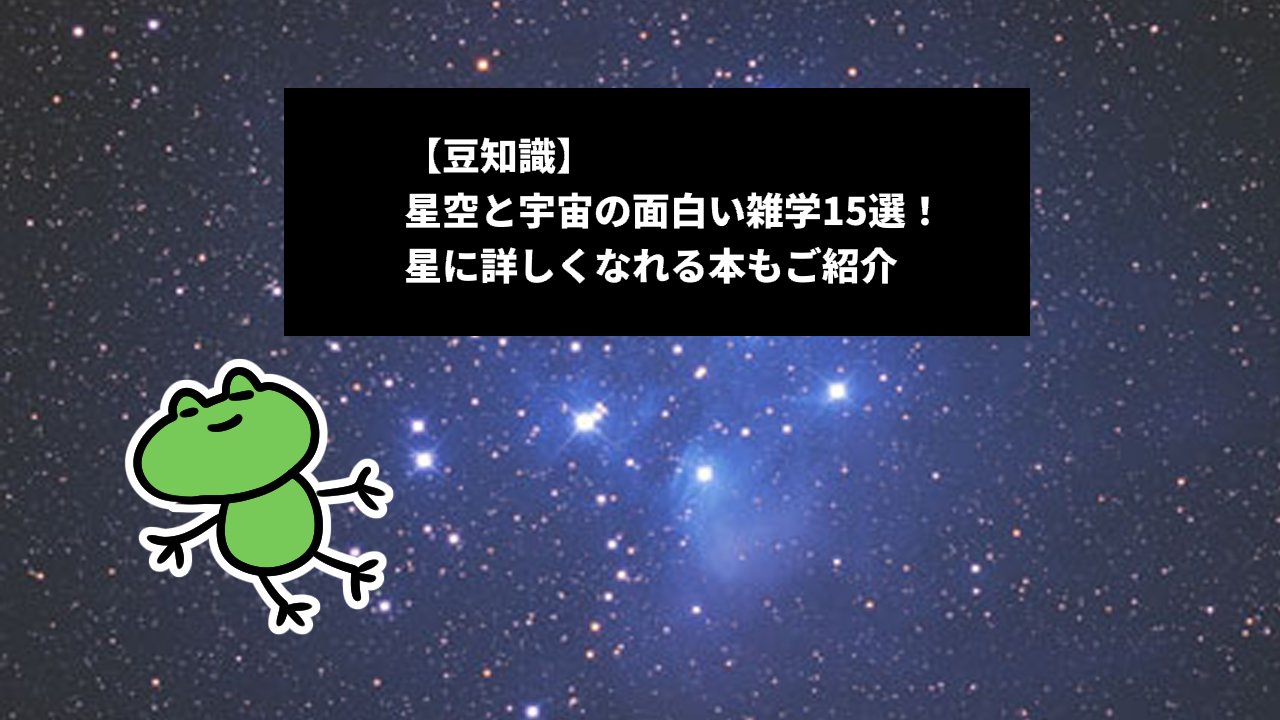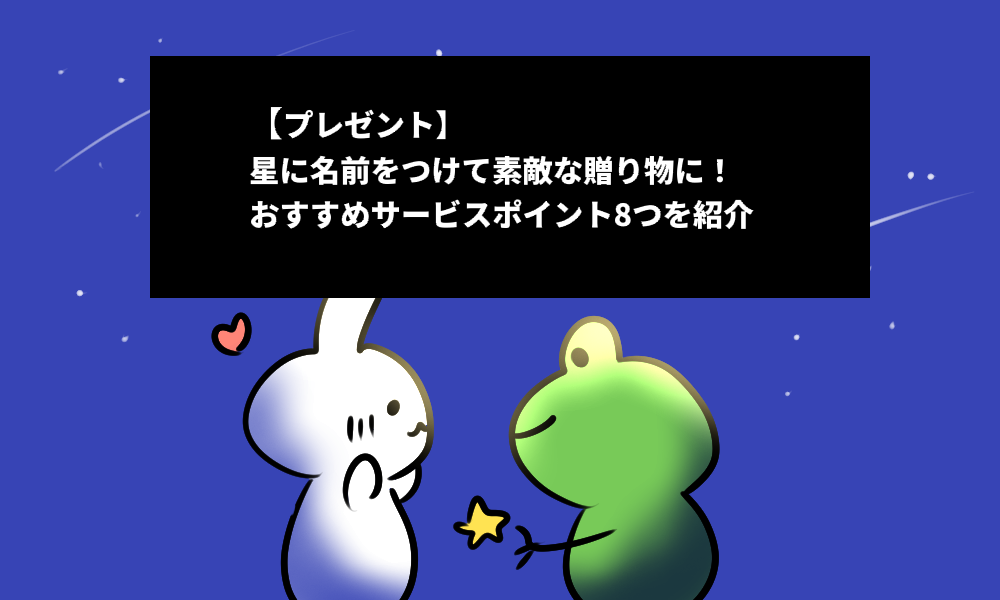普段何気なく見上げる星空に、色んな雑学や豆知識があることをご存知ですか?
・星と宇宙の雑学を知りたい
・星と宇宙が好きなので、もっと詳しくなりたい
・星に詳しくなれるおすすめの本は?

そんなお悩みの方は必見です!
この記事では、星や宇宙にまつわる意外な雑学や豆知識を厳選して15個ご紹介します。
読み終わる頃には、きっと星空を見る楽しみが倍増するはず。
また、星に詳しくなれるおすすめの本も一緒にご紹介するので、宇宙への興味がさらに広がること間違いなしです!
星空と宇宙の面白い雑学15選

星空と宇宙の面白い雑学には色んなものがありますが、ここでは15個ピックアップしてご紹介します。
・星は「生きている」ようなもの
・星の色は温度で決まる
・「一番明るい星」は地球の空では3種類
・流れ星はほぼ塵サイズ
・北極星は「永遠の星」ではない
・星の名前の起源はアラビア語やギリシャ神話
・太陽も恒星
・宇宙は「無音」な世界
・1日で見える星の数は約3,000個
・ブラックホールには「音」がある?
・流れ星に願いを込める理由
・星は核融合反応でエネルギーを生み出して光っている
・宇宙は「膨張」している
・北斗七星は星座じゃない
・星座の数は地域で違う
それぞれ詳しく解説していきます。
星は「生きている」ようなもの
星も私たちのように「生まれ、成長し、死を迎える」サイクルを持っています。
星はガス雲から生まれ、長い年月をかけて成長するもの。
たとえば、小さな星(太陽など)は寿命が長く、数十億年にわたって輝き続けます。
一方で、大きな星ほど寿命は短く、数百万年で超新星爆発を起こしてその生涯を終えることが多いのです。
星の色は温度で決まる
星の色はその表面温度によって変わります。
| 星の色 | 温度 |
|---|---|
| 青 | もっとも高温(約25,000℃以上)で、非常に若い星。 |
| 黄 | 例:太陽は中温(約5,500~6,000℃)。 |
| 赤 | 低温(約3,000℃以下)で、寿命が近い古い星が多い。 |
「一番明るい星」は地球の空では3種類
地球から見える「一番明るい星」といっても、実は条件によって異なります。
夜空全体で一番明るい恒星は「シリウス」で、冬の夜空に南の空で強い輝きを放っています。
これはおおいぬ座に属する星で、古代から多くの文化で特別な意味を持ってきました。
また、太陽系内で最も明るく見える星は「金星」です。
「明けの明星」や「宵の明星」として知られ、朝方や夕方の空に現れるその輝きは、恒星をしのぐほどです。
さらに、北半球の天頂付近で一番明るい恒星といえば「アルタイル」が挙げられます。
夏の夜空を彩る「夏の大三角形」の一角で、多くの人がその位置を目印に夜空を楽しんでいます。
流れ星はほぼ塵サイズ
流れ星の正体は、宇宙から飛んできた塵のような小さな粒子です。
これらは直径1ミリ以下のものがほとんどで、地球の大気に突入して燃え、明るい光を放ちます。
光を放つのはその小さな塵が高速で燃え尽きるため。
意外にも、流れ星はほぼ目に見えないサイズの物体から生まれているのです。
北極星は「永遠の星」ではない
現在、北極星(ポラリス)は地球の自転軸にほぼ一致しており、北の空で固定された位置に見えます。
そのため、夜空の中で常に北を指し示しているように見えるのです。
しかし、実はこの位置は永遠ではありません。
地球の自転軸は「歳差運動」と呼ばれるゆっくりとした揺れを伴っており、この運動によって約26,000年周期で北極星は移動します。

数千年後には別の星が「北極星」になる予定なんだって。
星の名前の起源はアラビア語やギリシャ神話
多くの星の名前はアラビア語やギリシャ神話に由来しています。
たとえば、「ベテルギウス」はアラビア語で「巨人の肩」を意味し、オリオン座の一部として有名です。
また、ギリシャ神話にちなんだ名前も多く、星々には古代の神話や伝説が色濃く反映されています。
太陽も恒星
私たちが普段見ている太陽も、実は立派な恒星なんです。
太陽は「G型主系列星」というタイプに分類され、これは宇宙で最も一般的な種類の恒星です。
太陽のような星は、膨大な数の恒星の中でもよく見られる存在であり、数十億年にわたって安定したエネルギーを放っています。
夜空に輝く星々の中にも、太陽と似たような性質を持つ星がたくさん存在しているのです。
宇宙は「無音」な世界
宇宙は「無音」の世界です。
地球上では音が空気中の分子を振動させて伝わりますが、宇宙には音を伝える空気が存在しないため、どんなに大きな爆発音でも聞こえることはありません。
たとえば、超新星爆発やブラックホールの周辺で起こる激しい現象も、実際には音としては存在しないのです。
1日で見える星の数は約3,000個
1日で見える星の数は、空が最も暗い場所でも、片方の空に約3,000個程度が限界です。
これは都市部などの明るい環境ではもっと少なくなり、数十個から数百個程度しか見ることができません。
地球全体では、肉眼で見える星の数はおよそ6,000個ほどであり、夜空に広がる無数の星々の中でも、私たちが見ることのできるのはその一部に過ぎません。
また、これらの星々のうち、実際に輝いているのはほんの一部であり、遠くの星々は非常に遠いため、その光が地球に届くまで何万年、何百万年もかかっていることもあります。
ブラックホールには「音」がある?
ブラックホールには「音」があるのでしょうか?
実際には、ブラックホールそのものは音を発することはありませんが、NASAはブラックホール周辺のX線データを音に変換することで、まるで音が存在するかのような結果を得ることに成功しました。
この音は、ブラックホールが周囲の物質を引き寄せている過程で発生する波動のようなものを基にしているのです。
その結果として得られた音は、低い「うなり声」や「ゴー」という音のようなもの。
この現象を「音響ブラックホール」と呼びます。
流れ星に願いを込める理由
流れ星に願いを込める習慣は、古代ギリシャ時代にさかのぼります。
当時、人々は流れ星が空の扉を開け、神々が地上を見下ろしていると信じていました。
そのため、流れ星が現れると、神々が人々の願いを聞き入れる瞬間と考えられ、願いを込めて星に向かって願うことが習慣となったのです。

また、流れ星が一瞬の光を放つことから、願いを叶えるための「チャンス」の象徴とされ、短い間に強く願うことで、願いが叶うという信仰が広まりました。
星は核融合反応でエネルギーを生み出して光っている
星は炎のように燃えているように見えますが、実際には燃焼ではなく、核融合反応によってエネルギーを生み出しています。
星の中心では非常に高温・高圧の環境が作られ、そこで水素原子がヘリウムに変わる「核融合」というが行われています。
この反応により膨大なエネルギーが放出され、そのエネルギーが星を輝かせる源となるのです。
核融合反応は、星の内部で数百万度にも達する温度で進行しており、その光と熱が何千万年、何億年にもわたって星を照らし続けます。
宇宙は「膨張」している
宇宙は今も膨張し続けており、遠くの銀河は私たちからどんどん離れていっています。
この現象は「宇宙の膨張」と呼ばれ、1920年代にアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルによって発見されました。
ハッブルは、遠くの銀河が私たちからの距離が増すほど、その光が赤く偏移する現象を観測し、これが「ドップラー効果」によるものであることを確認。
この赤方偏移の法則を基に、ハッブルは宇宙が膨張していることを示しました。この発見は、ビッグバン理論の基礎となり、宇宙の起源や進化についての理解を大きく進展させました。
現在では、この膨張は加速していることがわかっており、ダークエネルギーという未知の力がその原因だと考えられています。
北斗七星は星座じゃない
北斗七星は一般的に「星座」として認識されていますが、実際には独立した星座ではありません。
北斗七星は、おおぐま座の一部を構成する7つの明るい星であり、おおぐま座全体の中でも特に目立つ部分です。
おおぐま座自体は、古代から多くの文化で認識されていた大きな星座で、北斗七星はその中でも「柄杓(ひしゃく)」の形に例えられることが多いです。
日本では、この7つの星が「北斗七星」として親しまれ、北極星を探すための目印としても利用されてきました。
また、西洋では「ドーターズ・コイン」とも呼ばれ、さまざまな文化で重要な役割を果たしてきました。

北斗七星が星座として広く知られている理由は、その形がはっきりしていて目立つことから、古代の人々にとっては道標となる存在だったからです。
星座の数は地域で違う
星座の数やその認識は、文化や地域によって異なります。
国際的には、現在88個の星座が公式に認められており、これらは19世紀末に国際天文学連合によって定められました。
しかし、各地域や文明によって、星座の数やその解釈には違いがありました。
たとえば、日本の古代では、星を天の川や季節に基づいて独自に区分し、さまざまな星座や星群が伝えられてきました。
中国やインディアン・ネイティブアメリカンの文化にも、星座に関する独自の解釈があり、それぞれの星座が神話や物語と深く結びついています。
西洋の星座とは異なる視点で星空が捉えられ、たとえば、シリウスやオリオン座のようなよく知られた星座も、地域によって異なる物語を持っています。

このように、星座の数やその形、名前は、文化ごとの天文学的な理解や神話、宗教と密接に関連しているんだね。
おすすめの本「今夜星がみたくなる 夜空の手帳」
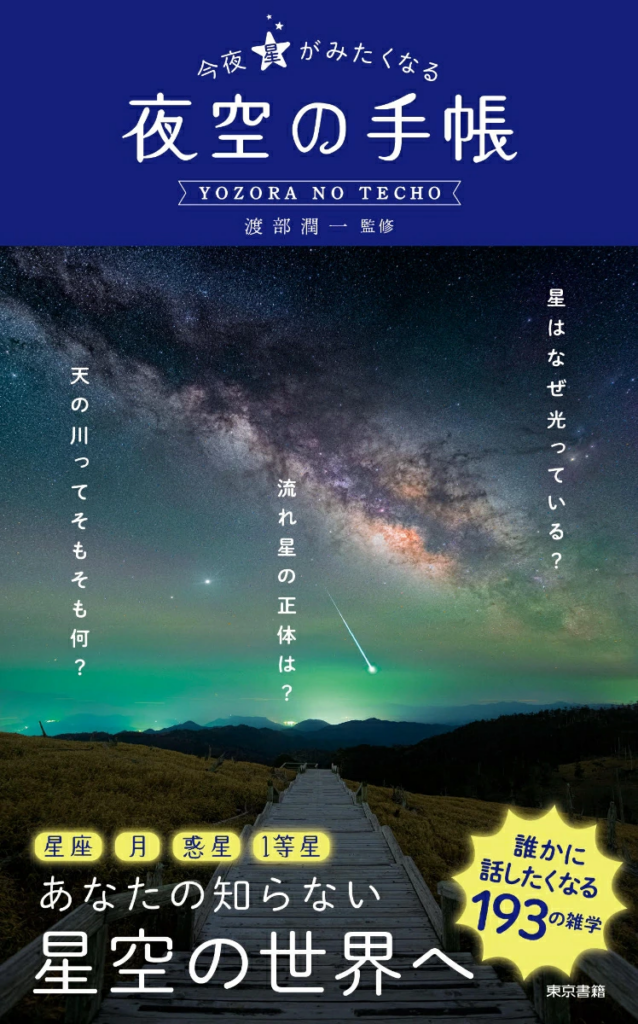
▲引用:楽天ブックス
星空と宇宙の雑学に詳しくなれるおすすめの本、「今夜星がみたくなる 夜空の手帳」をご紹介します!
星にまつわる193の雑学が収録されており、ビニールカバー付き&スマホサイズの判型で持ち運びにも便利。
また、綺麗な写真とわかりやすい解説で、星に詳しくない方もサクサク読むことができます。
【メリット】
・193のたくさんの雑学が収録
・持ち運びに便利
・綺麗な写真とわかりやすい解説
・星に詳しくなれる
【口コミ・レビュー一覧】
この手帳サイズに沢山の星の解説が詰まっています。
もちろん専門的なものに比べるとかなり簡易的な説明なんでしょうけど、星をライトに知りたいという人にとっては丁度良いくらいの説明になってます。また本自体のデザインも可愛らしく、日々持ち歩いて、気になった時に読んだりするのに良い感じになってます。
星が好きで色々知りたいって人にプレゼントで買いましたけど、すごく喜んでもらえました。
引用元:amazon
↓↓購入はこちら
 | 価格:1760円 |
まとめ
以上、星空や宇宙にまつわる様々な雑学や豆知識でした。
今、私たちが見ている星は宇宙のほんの一握り。
この記事で星に興味を持った方は、ぜひ天体観測をしてみてはいかがでしょうか?
↓↓あわせて読みたい